◆たのしい夜
足がぷらん、ぷらん、と揺れる。
誰かに運ばれてるなぁ、誰だろう。
控えめな音で開かれるドア、馴染んだ自分の部屋の空気。
「…いつもすまないねぇ。ありがと」
むにゃむにゃと礼を言うと、ニスロクは「起きていたのか…」
「…なんだ?」
「お祝いの料理たくさんありがとう。君も少し寝ていきなよ」
「なぜだ。私は片付けがある」
「片付けはあとで起きたらやればいいんだよ~」
「貴様の感覚だな…だから台所が散らかるのだ」
「そうかもねぇ。
私が袖を離さずにいると、
「ニスロクはおっきいねぇ」
「少し休んだら行く」
ニスロクはベッドのへりで長い手足を伸ばす。
「お父さんみたいだなぁ…」
「何?」
ニスロクの「何?」が「ナニ??」でちょっと面白い。本当に、
「子どもの頃もよく寝てたんだけど…
自分の立っていた世界が私を置いて全部どこかへ吸い込まれて消え
「夜中ひとりで泣いてると、
やさしくてちょっと不器用なお父さん。
街を点々とする私が新しいお店を開くともう足腰が悪いのにかなら
「…『たのしいを堪能する』のではなかったのか」
ニスロクの親指が私の頬を拭って、離れた。
「…たのしいよ。色々思い出せて、寂しいけど嬉しくて…。
「そうか…ならいい」
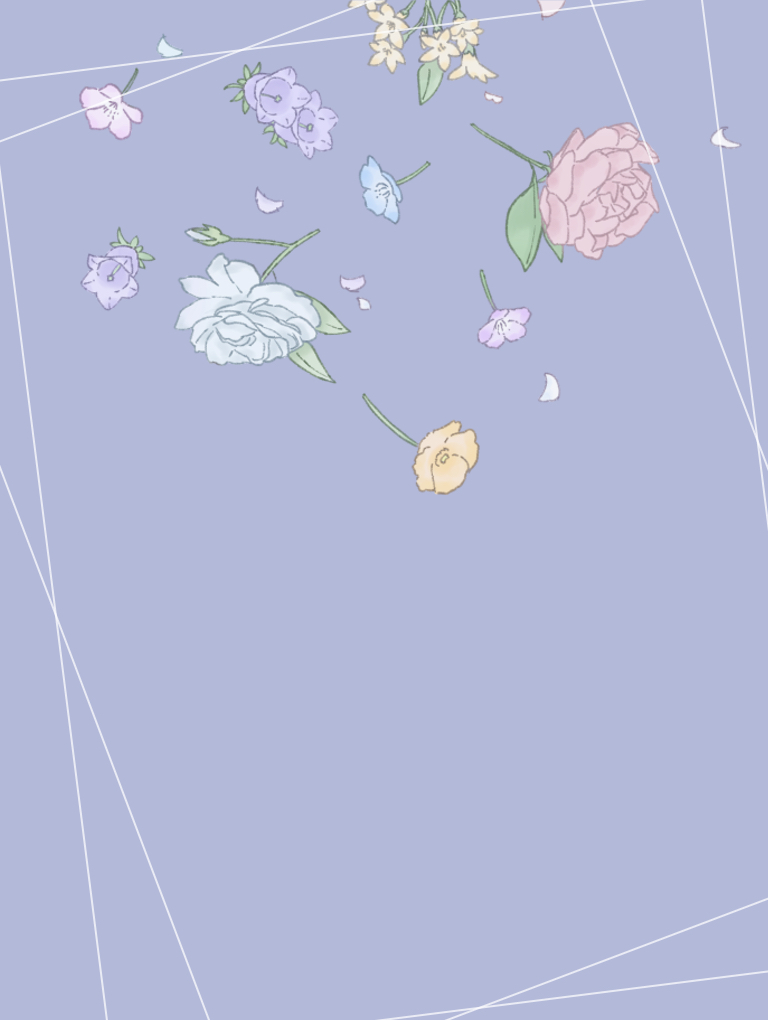
カテゴリー別人気記事