※18歳以上の方のみ閲覧をお願いします※
(※本編ネタバレまみれ。一度読まれた方もぱらっとめくり返してからお読みになるほうが楽しめるかも)
(※相変わらずなんでも許せる人向けのお話です)
♡喘ぎではなく通常喘ぎ版で読みたい方はこちら
Ω(オメガ)は運命のつがいであるαと結ばれなければやがて死ぬ――なんてロマンチックで吐き気のする嘘をバラまいたのは一体誰なんだか。見つけたらケツを思い切り蹴り上げたいとマイクは思っていた。
確かに、男女問わず子を孕むことのできるΩは受精しないまま成人を過ぎしばらく経つと、うなじに浮いた痣――通称『Ωの花』に脳をヤられる。正確には、痣に殺されるのではなく、脳が自然に機能を停止し、その予兆としてうなじに出来る痣が大輪の花のように大きくなる、ということなのだが。Ωだけに存在するその無慈悲な死は、Ωの間で『花に食われた』とか、『花屑になった』と表現する。
(くだらねー…)
哀れなΩ。α、βよりも一般的に知力、身体能力が低く、弱者として守られ、ヒート(発情期)に苦しみ、生殖の器とされる存在。”惚れたαに振り向いてもらわなければ花を咲かせて哀れに死ぬ生き物”だと同情の目を向けられる。生まれつきヒエラルキーの最下層。
しかも、Ωはなぜか習性的に一人のαにこだわる傾向にあるというのがいくつかの研究で指摘されている。遺伝子によってそう定義づけられたように。
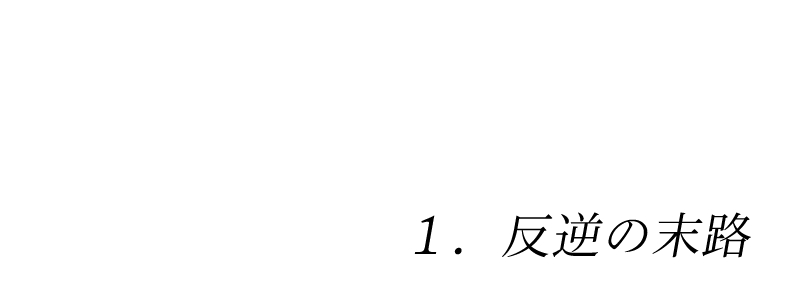
話を戻すが、マイクはΩの多くが若くして死ぬことについて、αと結ばれなかったことが理由ではないと思っていた。そんなものは己がいかに価値のある存在かを喧伝したいαが広めたストーリーだ。あるいは陳腐なロマンスの材料に過ぎない。
運命のつがいと結ばれず、孕まないまま命を落とすΩの大半は、脳機能が停止するまえに自ら命を絶つのだ。少なくともマイクが見てきた同胞のΩ達はそうだった。Ω性の奴隷とならないことへの反逆として。定められた運命への抵抗だった。
「一体誰が作ったんだろうなぁ…」
Ωという、哀れみを呼ぶ存在を。マイクはハンドルを握りながら指でとんとんと叩く。いらだちのサイン。今朝から耳鳴りがしているせいでカーステレオから流れる音楽がクリアに聴こえないせいかもしれない。せっかく音圧が尾てい骨に心地よく響いてきそうな良いスカが流れているというのに。
「ぁ…?」
助手席の相澤がうめくように声をあげた。マイクの独り言の断片を拾ったのだろう。おそらく、何か言ったか? と言いたいのだ。『花』が咲ききったΩである相澤を苛烈なヒートが蝕んでいた。マイクも同じだ、互いに末期のΩ。アクセルを踏む足が重く怠い。だがモーテルに帰らなければいけない。ミラー越しに、後部座席に寝かせた銀色のアタッシュケースが映る。やっと、日本から遥か遠いこのイギリスで生き残る可能性を手に入れたのだ。一生分の運を使い切ったんじゃないかと思うほどの偶然の連鎖の末の幸運。ここでつまらない事故を起こすわけにはいかない。
数十年前に英国3位の製薬会社が開発し、政府の承認が得られず製造を中止した薬。Ωの花を消す効能を持つ、恐らく世界唯一のそれが、未だに秘密裏に売買されている――モーテルで偶然得た情報を頼りに、郊外の孤児院跡地でそれを手に入れるとができたのだ。赤いキャラバンから顔を覗かせたサンドイッチ売りの男は、「同胞よ、あんたらはツイてる。こいつは98%の確率で効くぜ」と紙幣と引き換えに取引に応じた。緊張した面持ちのマイク達を見て、彼は「花のない暮らしは爽快だよ」と笑って染み一つないうなじを見せてくれた。
助手席のドアを開けると、顔にかかった昼間のあかるい日差しに相澤が億劫そうに目を開ける。眼球の動きはひどく鈍く、潤んだ眼差しはどろりとマイクの顔を見たが、差し出された手に頼ることなく車から下りる。二人は古びたモーテルの入り口をくぐり、閑散とした小さなロビーを抜け、エレベーターに乗り込む。ここは家族経営で雇われフロントマンもおらず、今頃オーナーは近くの庭の手入れでもしているのだろう。数字周りがやや黒ずんだ上階のボタンを押し、操作盤の下部に見知った日本メーカーの名前が彫り込まれていることにマイクはどこかホッとする。その瞬間、黙ったままだった相澤の体がぐらりと傾斜したのでとっさに受け止めた。
「っと、大丈夫?」
間近で見る禍々しい花の咲いた首筋は死の色彩に包まれているのに、しっとりと汗ばみ、強い生の匂いがする。マイクは相澤の脇腹に手をあて体を支えようとしたが、ぎこちなくすり抜けられる。
「…触られるとキツい…」
相澤はマイクから距離を取りエレベーターの壁に頭と肩を押し付けると、それだけ呟いた。先ほど車から降りる時もふらつきながら頑なに手を借りようとしなかった姿を思い出す。マイクは微かに苦笑した。ヒートの悶えるような苦しみに耐えている相澤にとってはわずかな接触でさえも自我を保てなくさせるのだ。
のろのろと上昇していたエレベーターが、チン、と間抜けな音を立てて五階に辿り着く。マイクは扉を開くボタンを押したまま相澤に先に出るようジェスチャーし、いつもより背の丸い黒いコスチュームの緩慢な動作を見送った。古びたボルドーの絨毯が敷かれた廊下にはひとけがない。おそらくこのフロアに他に宿泊客はいないのだろう、ここで三泊しているが掃除に来た小太りの黒人女性を除き人の姿を見なかった。周囲にひとけがないのはありがたかった。ヒートが発現したΩ二人のセックスなど行儀よく出来るわけがないので。

カテゴリー別人気記事