「あっ待った、スキンは」
「ない」
「…そうだった」
今朝出発前に抱き合った時に最後の一枚を使い切った。だから帰路で買い足そうと言っていたのに、熱で朦朧としていた上に薬を手に入れ浮かれた興奮でお互い失念し、ドラッグストアに寄る余裕もなく帰ってきたのだ。
だから相澤は、ゴムはもういい、そう言ってマイクを押し倒し体に乗り上げる。後々の腹痛などどうでもいい、薬が効かなかった俺たちはどうせもう死ぬのだから、という態度。マイクもそれを咎めることはしなかった。
(焦るな)
相澤は自分に言い聞かせた。
後孔に、マイクの肉茎が触れる。湿り気を帯びたそこは亀頭に熟れた肉輪を開かれ、ゆっくりと飲み込んでいく。
「っ……く……」
長く反りかえった肉竿を、一思いに飲み込んでしまいたい欲望。
駄目だ、そんなことをしたら意識が飛ぶ。
感じすぎる体から沸き立つ欲求を抑え込み、相澤は腰を徐々に下ろした。震える腿を抑えながら、ゆっくりと。
「ぁっ……、…」
先端を飲み込んだだけで甘いうめき声が上がってしまう。
ヒートの熱で過敏になっていることに加え、ここまでのセックス漬けの生活で絶頂にいたるまでの限界点は低くなっていた。強い刺激を避けようとしているのに、敏感な粘膜は勝手にマイクの竿をきゅうきゅうと締め付ける。たったそれだけで、相澤は早くも達してしまいそうになる。
(っダメだ、まだ…)
咄嗟にそう思っても勝手に粘膜が快感を拾ってきゅ、と圧を強める。容赦なく、甘い絶頂が押し寄せる。痙攣する中に搾られ、マイクも感じ入った吐息を漏らした。
体が衰弱している上に、快楽に弱くなっている自分を改めて実感させられ、相澤は唇の片端にくやしさをにじませる。だが、はあ…と色めいた低いため息を漏らすと、ぐったりとしながらも腰を上下する動きを再開した。
「少し休めば」
マイクの気遣いに相澤は答えず結合した腰を落とす。まだ先ほど達した余韻が抜けず、意識が半分飲まれている。一方で絶頂したばかりだというのに、もっと満たされたい、腹の中を穿たれたい、と飢えた体の芯が急かしてくる。肉茎の根本までひとおもいに飲み込むと、奥深くをぐっと押し上げられる圧迫感。腹の奥がひりひりした。また、絶頂がみえてくる。下腹部に途方もない快感が広がっていく。頭はマイクのペニスのことでいっぱいだった。こんなみだらな自分は知らない、知らなかった。相澤は唇を噛むが、すぐにはしたない声が漏れる。
「ッはぁ、は、…はあ♡ うぁ……っく」
相澤が肩を震わせ喘いでいると、マイクの苦笑がかすかに聞こえた。またイッたの、と言いたいのだろう。うつむいた視線の先で自らの肉茎が透明の粘液をつぷりと噴き出していた。小さな尿道口から徐々に染み出す先走りなのか潮なのか分からないそれが、相澤とマイクの陰毛を濡らしていく。
「っ…うご、く……」
相澤は重怠くなった体を叱咤するためにあえてそう呟いた。俺が動くけど、と言ったマイクの返答を無視してふたたび腰を持ち上げる。
「ぉ、あ゛」
ずぷん、と深くまで嵌りこむ衝撃。マイクの肉茎に引き摺られる粘膜が快感の悲鳴を上げていた。相澤は呼吸を乱し、大きすぎる快楽に身を折りながら繰り返し上下に腰を振るった。
「ぁ♡ あァッ…ぐ…、あ゛、ふ…♡」
「っ…、…」
自分の声が甘いのがイヤになる。歯噛みをするが、噛んだ歯の隙間から快感に裏返った声が漏れていく。相澤は唇を噛みしめ、腰をゆする。善い。善すぎる。下半身がぐずりと蕩けていきそうな感覚と、いつまでも消えない焦燥がないまぜになって襲ってくる。
「う♡ う゛、ぁ、ン♡」
「今さら声抑えんの…?」
相澤は口元に自分の手の甲を押し付けては夢中で腰を振るっていた。自分の声じゃないようで、ひどいこえだ、と思ったのだ。マイクの声はからかいを含んでいたものの、黙って相澤のしたいようにさせた。口を押さえているせいでふうふうと鼻息が荒くなる。はしたない喘ぎは抑えても、亀頭の先からは、ぴゅ、とぴゅ、と潮が際限なく噴き出す。腰が熱で溶けたように痺れる。また達した。気が狂いそうな快感は続いており、相澤にはどこからが絶頂でどこからがそうではないのか、もう区別がつかなくなっていた。しばらく腰を揺らしていたが、やがて動けなくなる。手の甲が自然とはずれ、締まりのない唇から唾液が糸を引いて零れたのが見えたが、指先まで脱力しており、拭うために手を上げるのもおっくうだった。
半目で見るうつろな景色の中。目の前でマイクが重たそうに上半身を起こすのが見えた。口元には何を言わんとしているのか、微かな笑みがある。相澤は何も反応できず、絶頂の余韻に沈んでいた。と、脱力した片腕が捉えられる。先ほどまで猿轡の代わりだった手の甲に、触れるだけの口づけ。相澤がそのことに注意を向ける間もなく、体を後ろに倒された。ひやりとしたシーツの感覚が火照った体に心地よく、相澤は、ふ…、と虚ろな溜息を吐いた。
が、すぐに奥深くまでペニスを押し込まれ、えづいた。
「っイ゛」
「お前のナカ、ぬるぬる過ぎてすぐ抜けちゃう…」
マイクが苦笑し、腰を揺らし始める。こちゅこちゅとぶつかる粘膜の音。ぬるんとした感触、再び柔肉を荒くかき分けられる感触に相澤は喉を反らして体をびくつかせた。休止を入れずに腰が打ち付けられ、相澤は、ひ、は、と悲鳴じみた声をあげる。甘く疼く刺激のつよさに腰は逃れようとするのに、両足はちぐはぐにマイクの下半身に絡もうともがく。
「っい、ぐ、いくっ、ぁ、あ゛ァ♡ …マ、♡」
相澤が垂らした粘液で二人の陰毛はびっちゃりと濡れそぼり、ピストンの間で聴くに堪えない音を立てる。マイクがただ相澤の体を貪るために腰を振る。恥骨のぶつかるにぶい衝撃。あ、あ、と呻くことしかできない唇。
「ぁ…っ…はあ、…ン♡ きもち…ッ」
マイクの上ずった声がセクシーに響く。無心で、ただ己が快楽を貪る喘ぎをあげながら、ふたりは交わった。肌のぶつかりあう音が粘液の湿り気を帯び、空気がどろりと濃密になる。溺れそうだ。いや、息ができないほど溺れていた。
相澤は何度も達した。Ωになってから連続でイく、ということには慣れたつもりだったが、きょうはこれ以上耐えがたかった。情けなくひんひんと泣きたいくらい、もう全身が快楽で擦り切れていた。相澤がたまらず身をよじると、マイクが「…もーいいの?」と尋ねる。尋ねながら、抜けかけた肉茎をずぷりと深くに嵌めなおした。上がる悲鳴。奥の気持ちいいところに当てられるとどうにもだめになる。終わらない、おわれない。
「あ゛ーー…ぅ、ぁ…っう、も…やめ♡」
「ケツ浮かして…」
身をよじった隙にバックに持ち込まれ、逃げを封じられる。言われたように尻を上げる気力はなかったが、シーツの上にうつ伏せの体を投げ出しているとマイクが勝手に腰を持ち上げてまた自身を深くねじ込んだ。
「ひ、イ、あ♡、ぁ、イ゛く、…っぁあ♡」
熟れた乳首まで抓り上げられ、目の裏に星が散る。
「あーごめん俺もう…限界…」
消太の中で精を放ち、マイクは、はぁ、と色めいた溜息を吐くと覆いかぶさってきた。背中の上で動きを止めてしまった体が熱い。だが自分の体も熱く、互いの体温が溶け合いどちらの方が熱いのかなど分かりもしない。
しばらくの静寂の後。相澤は気怠い目を薄く開き、モーテルの狭いツインルームが元の通り何も変わらず、現実に揺らぎがないことを確認した。――まだ、生きている。俺もマイクも…――背中に感じる熱は生命の証でもあった。相澤はほっとし、同時にひどくくたびれた気持ちになり、重い瞼を閉じた。しばらくの沈黙。やがてそれを破るようにハァーーーとマイクが大きな溜息を吐いた。職員室であれば、デカい溜息つくな、と小言を言うところだが、この状況では仕方ない。相澤も溜息をつきたかった。
「ツイてねーーー…」
相澤が黙っていると、マイクが相澤の横にごろんと寝そべり、碧色の目がくるりとこちらを向く。
「2%に仲良く二人で当たっちまうの、腐れ縁のなせる技かぁ?」
2%。あの薬を密売してくれたサンドイッチ売りの男が言っていたことを相澤は反芻する。
『同胞よ、あんたたちはツイてるぜ。こいつは98%の確率で効く』
薬を買った時、自分たちが効かない方の2%に当たるとは想定もしなかった。願望がそうさせたのかもしれない。100人のうち2人、さらに2人ともそこに嵌まりこむ確率も冷静になればそう少なくない割合だ。
相澤は目を閉じ、もう一度深く溜息をついた。できれば、マイクには助かってほしかった。Ωとしての運命に抗い続け、『消太』の死が消されてしまう現実に抗い生きてきた男がつまらないルーレットに当たって命を落とすのは酷だ。
とん、と眉間の間をかるく小突かれる。目を開けると、シーツの上に肩肘をついたマイクが覗き込んでいた。いつの間にかマイクの顔には普段と変わらない明るさが戻っている。
「難しい顔してるぜ? もー決まった運命なら残り時間はなんか楽しいことでもして笑ってない?」
「……」
「セックスはしたな? あとは…」
「気絶するまで飲む」
「ヒュウ。最高!」
マイクは体の怠さが吹き飛んだようにベッドから体を起こし、部屋の隅のミニバーを開ける。スキンは買い忘れたが、前日にビールはしこたま買い込んであった。
「消太何にする~?」
「軽いやつ」
そう答え終えた相澤は、目を見開いて立ち上がった。取り出したビール瓶を眺めるマイクの背後に立ち、うなじに触れる。
「何? もう一ラウンド?」
「違う」
するりと手が滑る。ブロンドの後ろ髪の間には滑らかな肌があった。
「消えてる」
Ωの花が。先ほどまでくっきりと浮き立っていたあの忌々しい痣が。
相澤は自分の首後ろにも手をやる。何もない肌の上をするりと手のひらが滑る感覚。何度も感じたあのざらつきがない。
「痣が消えた。おい、マイク」
相澤の言葉に何も答えないまま、マイクは相澤の肩を掴んで少し強い力で後ろを向かせる。確かめるようにうなじにそっと触れた手が、ひっかかりなく背筋へ滑っていく。歓声のひとつでも上げるかと思ったが、うるさい筈の男は静かなままだった。
はあ、というマイクの安堵が相澤のうなじにかかる。次いで、柔らかな唇が触れる。忌々しい痣の消えた、すべすべとした滑らかなうなじに。キスは随分長かった。唇が離れた後にひたりと触れたのは額だろう。マイクは祈るようにただそのままじっとしていた。
あの薬は想像していた以上に遅効性だったのだ。相澤は、フー…と深いため息をつく。二人一緒に助かったのもありがたいが、何よりもこの男に新たな罪の十字架を背負わせることにならずに済んだことにほっとした。
そして拳を握って振り返り、マイクの頬めがけて右フックを入れた。
「ぶっ」
不意打ちにマイクが呻き、よほど効いたのがよろよろと後ずさってベッドの上に倒れる。起き上がった緑の目はまるく見開かれ、何が起きたかわからないという表情をした。
「ったァーーー…消太くん?」
「お前を殴るために一緒にいくって言ったろ。お互い弱ってたから殴らなかったが、回復したら話は別だ」
マイクは仰向けで倒れたまま、記憶を探っている。そんなこと言ってたっけ? という顔だ。言った。死柄木達から逃走するために乗った選挙カーの中で。
「…イテェ…ヘビー過ぎて歯折れたかと思ったぜ…」
マイクが自分の頬を撫でながらいう。舌で奥歯を探るが、口の中が切れて血が出ているだけで歯は無事だった。相澤は頷く。
「加減した。土地勘のない海外で歯医者探すの大変だからな」
「絶妙な力加減をセンキュ…」
頬にじーんと痛みが響くのでマイクは眉間を寄せたままそう返し、やがて頬から手を外して言った。
「もっと殴ってもいいんだぜ?」
目的があったとはいえ、親友のお前を裏切った俺を。マイクは暗にそう言っていた。だが相澤はもう拳をしまっていた。
マイクは相澤の横顔をしばし眺めてから明るい表情を浮かべた。
「とりあえず、腹も減ったし自慢のポークチョップ食いに行くか」
モーテルの食堂にはゆったりと食事をする一人の老婆と、ビールを片手に談笑する二人連れの中年の男がいるだけだった。マイクの顔の怪我を考えると人が少ないのはありがたい。
席に着くと、キッチンから出てきた短いコック帽を被った淡いブロンドの男が、ハイ、と明るく挨拶をし、料理を運んでくる。こってりとケチャップに包まれたポークチョップ、山を作って盛られた大鉢の白ご飯。豆の煮ものなど3種類の総菜が丸テーブルの上に置かれ、ディナーセットは完了した。
「ワォすげぇ盛り…今時日本でもこんなの見ないぜ」
経営者は英国人だが、日本っぽい食事も楽しめるこのモーテルは日系人がよく訪れるという。中でも最も人気な名物料理がポークチョップ。和食とは言えないメインディッシュだが、和洋折衷のちょうどいい味付けになっているそうだ。
「にしても歯がいてぇ…」
「悪かった」
「謝るなら手加減してよ…」
「手加減しなかったから素直に謝れるんだろ」
「OK…」
ポークチョップは見た目通りこってりとした味付けに、隠し味として醤油が使われているようだった。日本を彷彿とさせるあまじょっぱい味に、マイクと相澤の頬がゆるむ。このモーテルは、朝食は塩漬けの牛肉とピクルスを挟んだソルトビーフ・ベーグルか、トマトソースで煮込んだベイクドビーンズが山盛りの伝統的イングリッシュ・ブレックファストの二択。英国の宿らしい食事だ。一方で夕食では日本人になじみ深い味を食べられる。偶然訪れたマイクにも相澤にも少し意外な、うれしい驚きだった。
「昔ここに泊まった日本人が作った味付けを今でも続けているんだよ」
吸い込まれそうな灰色の瞳をした老人が二人のもとへやって来て、そう言った。モーテルの主人だ。好奇心に満ちた大きな目が、マイクと相澤の顔をじっくりと眺め、人懐こい笑みを浮かべる。Mr.ヨーダ。顔立ちも、英国人にしては低い背格好も、宇宙を舞台にした有名映画の人物に似ていることから、彼は初対面でそう呼んでくれと笑った。花を消す薬の存在について、マイクと相澤に教えた人物でもある。
「そうなんスか。昔泊まった日本人って、コックさんか何かですか?」
「いやぁ、『革命家』だと言ったね。ハッハ、面白い男だったよ…私も子供ながらに覚えている。下手くそな英語、言葉よりも意思を強烈に伝えてくる爛々と光る目」
Mr.ヨーダは思い出深そうに答えた。このモーテルの先代経営者だった彼の父が気に入った異国の流浪人。革命家と名乗ったその男は日本からΩの花を消し去る薬を求めてこの英国にやってきた。このモーテルから十数キロの地点に、製薬会社の研究所があった。彼はその製薬会社が薬を開発した、との新聞記事を日本で読み、一縷の望みを託し英国に来たのだという。彼のうなじにも大輪の花が咲いていた。
「だが彼は薬を手に入れられなかった…開発された薬は国の承認を得られず出回ることがなかったからね。何か『不祥事があった』とかでその研究所も閉鎖が決まっていたし」
「…キナ臭ぇ話ですね。公権力の暗躍を感じる」
「そうかもしれないね。途方に暮れた彼が泊まったのがこの宿だ。私の父は彼から話を聞き、秘密裏に薬を手に入れた。…研究所に父の友人が勤めていたのでね」
おかげで革命家の男は一命を取り留めた。彼は『苦しんでいる同胞が大勢いる』と日本に薬を持ち帰りたがった。が、未承認薬は当時の研究チームの一部の人間がこっそりと作っただけで量がない。温度管理も難しく、長期の輸送に耐えられない。彼は諦め、手ぶらで帰国せざるを得なかった。
「そして彼がここを発つとき、私の父に礼として振舞ってくれたのがこのポークチョップというわけだ」
日系人が食事利用だけで食べにくることもあるし、意外に英国人にも人気なんだよ、とMr.ヨーダは笑った。マイクと相澤は一連の話を聞き、彼が自分たちに親切にしてくれた理由がわかった気がした。宿泊する外国人に対して当然求められる身分証明書を出せなかった身元不明の日本人二人を受け入れ、さらにΩであると知れば薬の存在を教えてくれた理由が。
「運が良かったな、俺達…」
マイクは運命に翻弄され続けていたここまでの緊張が一気に解けたように、安堵の溜息まじりに呟いた。Mr.ヨーダは微笑み、テーブルの上で空いた一枚の皿を下げながら、
「君たちの顔を見て『革命家』の彼を思い出した…なんとなくだがね。運命に屈しまいという目の光だな、ふふ」
「…彼とはその後も連絡を取り合っていたんですか」
尋ねた相澤に、Mr.ヨーダはNo,と穏やかな声色で答えた。
「別れ際、気遣う父に彼は『帰国してしばらく身を隠す』と言っていたよ。何をしたかは知らないが、日本では自由に外を出歩ける立場じゃないようだったね。海外との連絡も自由にとれる環境じゃなかっただろう」
隠れ家…と聞き、相澤の頭になんとなく暗い海に浮かぶあの孤島が浮かんだ。マイクが少し改修したものの、暖炉と、思想の火が滾る本棚のある古びた小さな家。………まさか、偶然にそんなことがあるはずもないが。
朝食を終えた二人はモーテルの外へでた。建物の右横の駐車場にはおそらく唯一のほかの宿泊客の車なのだろう白いローバーがぽつりと止まっており、その隣にレンタカー屋に賄賂を握らせて借りたマイクと相澤の赤いオープンカーがある。久しぶりの晴れ間に赤い車体は艶やかに光っていた。モーテル前の片側一車線の国道は車どおりが少なく、澄んだ空の下はるか遠くまで路面が続く。どこにでも行ける――晴れた空も、遠く続く道も、高熱から解放され軽くなった体も、そう言っていた。
Mr.ヨーダから借りた周辺の観光ガイドブックを手にしたマイクは道路脇で足を止めると、横にやってきた相澤に「どうする?」と尋ねた。
「もう教会は嫌だぞ。飽きた」
相澤の答えに、マイクは困ったように笑った。
「じゃなくてよ。お前はもう国際指名手配のヴィランの元からいつでも逃げ出せる自由の身だけど? って話」
…今更そんなこと言うな。
そう思いながら、相澤は無然とした表情を返した。
「犯罪者兼友人でもある。どっちの意味でもお前から目を離すわけにはいかない」
何度も死にかけた。ヒートの熱で苦しみながら、すがるように肌を重ねた。ともに生き延びたことが奇跡だというのに、マイクはまるで先ほどまでのことを忘れたように他人になろうとする。相澤はむかむかとしていた。散々人を引っ張り回しておいて、今更そんなこと言うな。
ふと相澤の脳裏に、マイクがあの孤島に作っていた小さな手盛りの墓が浮かぶ。マイクが連れていくと決めているのは自分ではなく、あの『消太』なのだ。それは生きている相澤消太――俺、に対するマイクの気遣いかもしれないが、同時に死んだ『消太』への忠誠でもある。
「…お前がいつ死ぬかも分からないしな」
相澤は付け足し、鋭い目でマイクを見た。マイクが花を消すことに必死になっていたのは相澤のためで、自分が生き延びるためではない。日本で政府への復讐を遂げたマイクは生きる意欲が希薄になっている気がした。
相澤の指摘にマイクは肩をすくめただけで返す。
「…お前が俺と一緒にいることを選ぶのはそりゃお前の勝手だし、こっちも大歓迎だがよ。けど、俺は日本に戻る見通し立たないぜ? いつまでも一緒にいるわけにもいかないでしょ」
マイクの暴露劇が拡散され、国民の反対から政権は変わった。だが新しく第一党になった元野党はまだおぼつかない。今後マイクに対してなんらかの恩赦が下される可能性も0ではないが、当面は見込めないだろう。前政権の政治家たち、公安など権力側にマイクを恨む者も多いはずだ。
「日本に戻って服役する気はないのか。刑期が明けたら自由だ、全部やり直せばいい。ヒーローも教職も」
「ヴィラン連合の手伝いしてた元服役囚が教職なぁ。ヴィランから助けてくれたってどの面さげてヒーローやってんだって思うけどな、俺がキッズなら」
相澤は黙った。
自分の言ったことが理想論なのがわかる。いや、自分自身の願望なのだと。元通りお前とバカ話しながらヒーロー兼教師して暮らしたいんだ、という口に出来ないことばが喉の奥でわだかまっていた。
「お前の気持ちは嬉しいが、…非合理だぜ? ヒーロー」
…言葉に出せない感情が上っては、また飲み込まれて腹に落ちていく。マイクは相澤の表情を眺め、ぽん、と背中を叩いた。
「牢屋のまずい飯食うのやだしな。メインもサイドも選べない、ビアがピルスナーかアルトかも選べない日常ならここで野垂れ死にたい」
…連合だって俺を許さないだろうしな、と軽い調子で付け足された言葉。そうだ、死柄木はマイクを殺すだろう。自分が殺されれば日本に戻るよう説得した相澤がどう思うか。そこまでこの男は考えているのだ。マイクは小さく溜息をついて言う。まるでこれで話は終わりだとでもいうように。
「俺の話はともかくさ…お前には待ってる奴がいっぱいいる。まだまだお前のきッッつくて優しい愛の鞭を欲する雄英の卵たちも、まだフォローが必要なお前の愛弟子もサ。抹消の個性だってヒーロー側の貴重な戦力だ」
「……」
確かにそうだ。あぁわかった、じゃあな、とこの場を去るべきなのだ。普段の自分ならそれができていただろう。マイクがこの場を動きたがらない以上、この非合理な問答を続けても仕方ない。
そう思う一方で、相澤はある若き日の情景を思い出していた。中3の修学旅行の夜、森でうずくまる山田ひざしの背中を。こいつはあの時も言っていた、『俺は大丈夫』『先に戻ってろ』と。もしあの時ひざしがΩであることに気付けていれば、孤独な苦しみに少しは手を伸ばせただろうか。ヴィラン連合と行動を共にする選択を、何か違うものにできたかもしれないと考えるのは浅はかだろうか。あの夜の澄んだ星空と相反するように、相澤の胸のうちには悔恨が積もっていた。
「…お前はどうするつもりなんだ。イギリスに残って」
「特に決めてないけど、パブ巡りでもするかね。スコッチウイスキーの酒蔵巡りもいい…そういやストロベリーフィールズがこの近くにあるから記念写真撮りに行くのもいいかもなー、レノンとマッカートニーに思いを馳せるならリヴァプールにも足伸ばすのもあり。ハァン英国って意外と回るとこいっぱいあるよな、予定立てるだけで一日終わっちまいそう」
ぺらぺらと喋るマイクが、相澤を心配させないように饒舌になっているのが分かった。別にお前が居なくても俺は楽しくやるから大丈夫だぜ、と言いたいのだ。
(今更俺がお前のそんな小芝居に騙されると思ってんのか)
もう相澤は意地でも納得したそぶりをみせてやらないことにした。納得して立ち去るなんて論外で、草の生えたモーテルの駐車場の地面に根を張るように両足を踏ん張り、頑として動かず、マイクから視線を外さない。マイクもその意思に気づいたのだろう。滑らかな口調が止んだ。
「……あとは、墓作ったりな」
賑やかさの消えた、静かな呟きだった。
「…『消太』のか」
「うん」
「墓っつったってあの島と違ってこの国にお前の土地はないぞ。土地を借りるにしたって身分証明書もない」
「そりゃそうだ。……正直ノーアイデアだけど…そうねえ、親切そうなモーテルのおじさんに相談するかね」
この駐車場の端にでも土を盛って作るのか? いずれにせよ現実的ではないように思えた。まだマイク自身もあまり考えていないのだろう。
マイクの気持ちもわからなくはない。政府直轄の実験によって失われたαの少年・消太の死を、なくしなくないのだ。消太が体に合わない薬剤を打たれ、結果として隠ぺいのために肉体の大半をゴミとして焼却処分されたという事実を、その苦しみを…自分が秘したまま抱いていた感情を、今の相澤消太が生きているからといって忘れたくないのだ。あの孤島で、月命日のたびに空っぽの墓の前で夜空を眺めていたマイクの行為は第三者から見ればままごとかもしれない。だが本人にとっては目の前の日常を離れ過去に思いを馳せるなくてはならない時間。親友の魂を悼むことは、消太を無残な目に合わせた不条理な体制への復讐の狼煙を上げ続ける行為でもあった。
マイクの『消太』への気持ちは中学で時を止めてしまったように純粋なままだ。まるで薄いガラスの器に閉じ込めた過去をひっそりと何度も見返すような純粋で一途な感情。月命日のたびに姿を消し、空っぽの墓と過ごしていたマイクのそんな性質を相澤は否定するつもりはなかった。自分自身が『消太』であると主張するつもりも、ない。頭部も脳も、つまり心も引き継いだ自分は相澤消太に他ならないが、Ωの山田ひざし少年が秘情を抱いていたαの少年ではないのだから。相澤はただ…マイクの気持ちを穢すことなく、そばで見つめていたかった。それは生徒に向ける視線とはきっと違う。できれば幸せでいてほしい、という願いは同じだが、ただそれだけではなくもっと利己的なものだ。
「…なら俺を参れ」
相澤が唐突に呟いた言葉にマイクは、は? と口をぽっかり空けた。
「『消太』の頭蓋骨は俺の中にある。生きた墓標だ」
大事にしろ、とにやりと笑う相澤の顔を、マイクはしばらく口を開けたまま眺めていた。生きている人間を、親友を、墓扱いするという発想は突飛すぎる。
「…お前はそれでいいわけ? つまり俺があの『消太』を大事にしてんのは俺の自分勝手な…妄想、みてーなもんかもしれないんだぜ? それを…」
「信仰のことは知らん。が、生き仏みたいなもんだろ。早速フィッシュアンドチップスでも供えてもらおうか」
ニィと相澤は歯を見せて笑った。
目の前でマイクの碧色の目がゆらめき、見とれた瞬間に強く抱きしめられていた。骨がきしむ力強さと、「…センキュ」という感嘆。相澤は黙っていた。勝手に目頭が熱くなるのは、運命にがんじがらめになった男の鍵穴をやっと探し当てることができたからだろう。
「そういう消太が、…お前が、中学の頃からずっと好きで」
だからお前を裏切った最低なヴィランはここでバイバイして野垂れ死ぬのが綺麗な幕引きだったのにさ、と呟いてマイクが相澤に口づけた。噛みつくような接吻に相澤は何も答えられなかったが、マイクの浅はかさを鼻先で笑った。そんなこと許すわけがない。
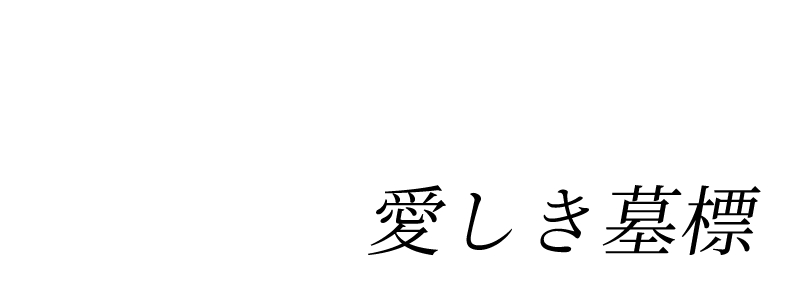

カテゴリー別人気記事