メギドはヴィータ(人間)のような感情を持たない、と言われている。
だからアガレスは、恋仲であるはずのニスロクがヴァイガルドに来た当初一流レストランの味を知りたいがために幾人もの男に抱かれ金を稼いでいた、と知っても特に驚かなかった。穢らわしく思うことも、傷つくこともない。──料理欲求に突き動かされ生きている男なのでそういうこともあるだろう──と受け止めるだけだった。他愛のない雑談の、話の流れだ。話したニスロク自身も気にした様子はなかった。
ただ、アガレスは普段自分を抱く男が過去に他人に抱かれていた事実に少し興味を持った。運命に従っていた自分が抗うことを知ったように、状況の反転、という現象はしばらく前からアガレスの関心事だった。だから「私もオマエにそのような形で触れてみたいものだな」と何気なく呟いた。それが叶っても叶わなくてもどちらでも構わない、というつもりで。
もう雑談を終え、コックコートを脱ごうとしていたニスロクはその言葉を拾い、少し怪訝な表情をした。自分が今日予定していた”メニュー”の順序が狂わされることへの若干の不快感だった。
「無理にとは言わん。気にするな」
「……いや、まあいい。少し待ってろ」
久しぶりなので準備に時間がかかる──そう言いながらニスロクは眉間の皺を解くと、意外にもあっさりと部屋を出て行く。アガレスは自分で言ったものの彼が了承するとは思っていなかったので、ベッドの上で胡座をかいたまましばし固まっていた。どうやら、過去に赤の他人に好きにさせたのに今恋仲であるはずの貴様の希望を断るのもおかしな話だな、という彼固有の妙な”道徳”が働いたようだった。
「準備は済ませてある。好きにするといい」
ベッドの上に腰を落としたニスロクは正面に座るアガレスに少し投げやりにそう言った。彼が金を稼ぐために床を共にした男たちにもそう言ったのだろうか──そんな雑念に囚われながらも、アガレスはニスロクに顔を近づける。ニスロクがふっと笑った気配がした。からかうようでもあり、どこか嬉しそうでもあるそれは(貴様は始めに接吻をするのだな)と言いたげだった。アガレスは頬がじわりと熱くなるのを感じながらニスロクにそっと口付ける。唇を合わせ、柔らかな舌の抱擁へ。その下で、ニスロクが自分のコックコートのボタンを外す気配がした。舌を絡ませながらアガレスも誘われたように金装飾のボタンへ手を伸ばす。アガレスの指がボタンを外し始めるとあとは手を下ろし任せるニスロクの様子が、手慣れた娼婦のように思えてアガレスの鼓動を落ち着かなくさせた。
いつも分厚いコックコートに包まれた男の体は日差しを知らない色だ。アジトには素体の違いからもっと色白の者もいるが、ランプの火に照らされて淡く光を跳ね返すニスロクの肌もアガレスからすれば同等に見えた。膨らみのある胸の筋肉、腹筋の溝を辿り、いつか幻獣につけられたという脇腹の傷を指でなぞる。その向こうで彼の陰茎がゆるやかに勃ち上がっているのを見てアガレスはどこかほっとした。
「ぁ、…」
手で体をまさぐりながらニスロクの耳に口付け、舌を這わせると微かに声が上がる。熱い息を押し当て、耳の裏へ唇を滑らせ、その小さな丘陵をついばむ。接しているニスロクの脚が焦れたように僅かに擦り合わされたのを感じた。
アガレスは彼の胸に指を這わせる。乳首は小指の爪の先ほどのちいさな粒で、見過ごしてしまいそうになる。アガレスがそっと摘まみあげて指の腹でやさしくこすると、ニスロクは微かに息を漏らした。薄紅色が如実に赤みを増すほどに指先で弄ると、ぷつりと粒立つ。ニスロクは声を上げることはしなかったが、アガレスの褐色の指が自分の乳首を弄るのを熱っぽく見ていた。官能を感じ、もっと触って欲しいと思っているようだった。
アガレスは勃起し熟れた乳首に顔を寄せる。舌で弄ってもっと感じさせてやろうとした。しかし身を委ねていたニスロクの肩がぴくりと跳ね、アガレスを制止した。
「そこはもういい」
「なぜだ」
オマエの体は欲しているのに、という趣旨で見つめ返すと、ニスロクは珍しく言いよどんでいた。早く交わりたいのか、乳首を舌で嬲られる刺激を恐れたのか。恐らく両方だろう、そう微かに予感しつつアガレスは答えを待たずにニスロクの乳首を吸った。先ほどから粒立ったままの先端は唇で挟めばふにゃりと柔らかく形を崩す。刺激にニスロクの胸がぶるっと震えた。
「っ、ぁ」
粒立ちを舌先で押し潰し、転がすように愛撫すれば、ニスロクが息を詰めた。尖りに軽く歯を立てれば白い首が仰け反ったのが分かった。気配だけで、ニスロクが快感に悶えているのが分かる。──どんな顔をしているのだろう。顔を見たくなりアガレスが頭を上げると、怒っている時以外はあまり表情に乱れのない顔が緩んでいた。ほんのりと血の気を増した唇はうすく開いたままで、溶けた飴玉のように熱情の膜を張った瞳には普段の気高さや厳格さが抜け落ちていた。(オマエもこんな顔をするのだな…)と静かに感じ入っていると、ニスロクがアガレスの髪をくしゃと掴んだ。
「アガレス…いい加減にしろ。抱くなら早く本題に入れ、私は気が長くない」
「そうだな」
それは知っている、というただの相槌でしかない返答を返すと、アガレスはニスロクが先程反応した耳の裏に口付け、強く吸った。同時に唾液で濡れた小さな尖りを指できゅっとつねると、ニスロクの腰がシーツから跳ねた。見れば彼の陰茎はもう硬く勃起していた。手を伸ばすと、触れた先端がぬるついて指が滑った。ニスロクの陰茎は色素が薄く、長く太い。張りつめた幹を指で包み、上下させると亀頭から溢れていた透明な液体が、ちゅく…と控えめな音を立てる。刺激にニスロクが体を強張らせる。触れている肌の体温がじわりと上がった気がした。
「アガレス、もういい…」
「オマエは普段こんなに濡らしているのか…?」
辱めるつもりはなく、アガレスはただの感想として呟いた。普段はニスロクに入念な愛撫を施され、挿入される時には彼がどんな状態であるか気にかける余裕がなかった。ニスロクはいつも、こんな風に、先端から焦燥の蜜を垂らして私の身に分け入っているのだ──そう思いながら血管の浮いた幹から膨らんだカリ首までを熱の籠もった手で扱いていると、唇を噛んでいたニスロクが少し焦ったように言った。
「っ待て、出てしまう」
「出せばいい…」
銅鐘のように低く響く静かな声で、アガレスは手を止めないままそう返した。ニスロクが金色の瞳を見開いたのを、綺麗だと思った。
「っ、…!」
手の中に温かい迸りが噴き出す。ニスロクは唖然とし、目を覆うように片手を顔に乗せた。彼にとっても行為の最中、しかも序盤に射精してしまうのは初めてなのだ。アガレスは手のひらからこぼれ落ちそうになった精を舐め取る。不思議と甘い後味がした。
「甘い」
「…何がだ」
「オマエが出した精の味がだ」
「…それはそうだろう、私は純正メギドだ。貴様と違ってヴィータ体ではない。多少の違いはあるだろう」
早く話を済ませたいのかニスロクはさも当然のように言ったが、アガレスはすんなりと納得できない。それは理由になっているか?もしそうだとしたらなぜ純正の精液が甘いということになるのか?しかも何故かハチミツに似た甘さだ…──考え始めた眼前に、身を起こしたニスロクの顔が迫った。
「貴様に付き合っていたら朝になってしまう。気を散らすな。抱きたいと言ったのなら私に集中しろ」
目の前で凜とした眉が不機嫌そうに寄ったので、アガレスは自然と微笑んだ。
「いや、オマエのことしか考えていない」
事実そうだった。ニスロクはまだどこか不満げな顔をしていたが、アガレスの回答を一応は認めたのかベッドで俯せになった。
「準備は済ませてあると言っただろう。…あまり待たせるな」
「ああ、すまない…」
アガレスは正面からニスロクを抱くつもりだったが、俯せになった彼の希望を受け入れることにした。逞しい背幅、大包丁を振り下ろす背筋。ニスロクの体は女のそれとはほど遠いが、引き締まった腰からなだらかに弧を描く尻に自然と目が吸い込まれる。体の他の部分よりも白く、手で触れると程よい肉付きがむっちりと心地よい弾力を返し、肌は滑らかだった。
「尻が綺麗だな…」
「なんだ?」
想定外のことを言われたのか、ニスロクが怪訝に聞き返して振り返る。
「尻が綺麗だと言った」
アガレスは(顔が綺麗な男は尻も綺麗なのだな)と漠然と思った。ニスロクは初めて言われたことのようで暫し沈黙していたが結局、…そうか、と素直に受け止めた。
アガレスの中指が奥まで入り込み、その感触にニスロクは小さく呻いた。骨張った長い指だ。粘膜を探るように奥へ滑り、また引き抜かれる。いつのまにかニスロクの肌はシーツの繊維をうとましく思うほど過敏になっていた。過去に他人に体を許した時には感じたことのない昂ぶりだった。
「っ…、」
アガレスが触れている箇所の粘膜がヒリつくように疼き、思わず尻をもじつかせる。いつも見下ろす顔を見上げる奇妙な感慨。黒目の細い目に真剣な光を宿し前戯に没頭するアガレスはまだ年若い青年のように見えた。
「…ここか」
指が内部の少し膨らんだしこりを探り当てる。指の腹でそこを撫で、人差し指も差し入れて二本の指で柔肉を挟み、ついばむように擦り上げる。と、ニスロクの体温が急に上がった気がした。彼を見ればシーツにうつ伏せる表情は見えないが耳が赤い。
「苦しいか?」
「…っ…早く次の工程へ入れ…」
ニスロクに先を急かされ、アガレスはゆっくりと指を引き抜いた。普段自分を組み敷く男が素直に白い尻を向けていることに、どこか夢のような、倒錯的な感情を抱く。しかし彼の内部は潤滑油でぬるりと湿り、その淡く赤らんだヒダは待ち侘びるようにひくついていた。
「では…」
そそり立つ陰茎を臀部の谷間に乗せる。アガレスの陰茎は褐色に淡い桃色を染み込ませたような色で、カリ首は張り出し、ニスロクのそれに負けず長さ故のずっしりとした重量感があった。挿入される立場としてはじめて肌に触れたその熱と質量に、ニスロクが身じろぐ。
「大丈夫か?」
「…問題ない」
微かに緊張を含んだ硬質な声だったが、彼が問題ないと言えばアガレスはそう受け止めるしかない。正直、抑え込んでいただけでアガレスも随分前から強い焦燥にかられていた。指を包んだニスロクのぬめり気を帯びた温かい粘膜を早くこの身で感じたい、という甘えと飢えの入り交じった欲求。そしてニスロクという高貴で美しい男を支配したいという今まで感じたことのなかった雄としての欲求が膨れ上がっていた。
「はっ…、…」
幹を抑えてそっと亀頭を挿入していくと、ニスロクが息を吐き、堪らなそうにシーツに頬を擦りつけたのが見えた。アガレスも深く、細く息を吐く。そうしなければ勢いに任せた結合をしてしまいそうだった。ぬるついた粘膜の壁を少しずつ押し広げ、根元まで挿入すると充足感に腰がジンと甘く痺れた。尻たぶに触れたアガレスの陰毛のちくちくとした感触にニスロクも微かに身じろぎする。
「動くぞ」
今度はニスロクの返事を待つ余裕がなかった。
「あっ」
ニスロクの裏返った声が響いた。唐突な刺激に驚いたのだろうが、普段低く落ち着いた喋り方をする彼がそんな声を出すのは意外だった。腰を引き、肌を打ち当てるように穿つと、微かな甘い快感に包まれたが、すぐにそれは焦燥に変わる。
「っ、…ぅ、…っく……、…」
ニスロクは一度不本意な声をあげてしまったことに恥じ入ったのか、あるいは深夜であるため隣室を気にしたのか、枕に深く顔を埋め声を抑えていた。三つ編みの端から覗くうなじが汗ばんで微かに光っている。その肌を見ていると、噛みつきたい、という欲求が沸き上がった。そんな動物じみたことを思うのは初めてで、アガレスは荒い息を吐きながら微かに自嘲し、俯いて白い肌から目をそらした。
「アガ…、…っ、…」
「ん…?」
口元を枕におしつけたままのくぐもった声がアガレスを呼ぶ。尋ね返しながらも腰を止めることはない。臀部と下腹部がぶつかる乾いた音に、二人の蜜で濡れた粘膜が気泡の混じった鈍い水音を立てていた。部屋の空間に響くその音に邪魔されて声を聞き取れないため、アガレスはニスロクの頭に顔を近づける。
「どうした」
アガレスが完全に密着し覆い被さる格好になり、陰茎がより深くまで押し入ったためニスロクは枕の中で黙ったまま一拍置く。
「……すこし休ませろ…」
斜め上から見下ろすアガレスを振り返ったニスロクの顔は快感にとろけた、というよりも疲れているように見えた。いつも凜とした鋭い眼差しはまだ辛うじて正気の光を残してアガレスを見ていたが、表情は顔を上げるのも怠くて堪らないと言いたげだ。アガレスは自分が感じていたより長い時間ニスロクを無言で穿っていたことと、ニスロクがそれにより何度か絶頂を迎えたらしいことにその時初めて気付いた。
枕に擦れて乱れたのであろう長い前髪が唾液で濡れた唇に張り付いていたのでそっと払い、毛束をいつもと同じ方向に直してやる。
「オマエは普段私を休ませてくれないだろう」
怠そうにゆっくりと瞬いていたニスロクは、その意味を理解するのに数秒かかったようだった。その間にアガレスは背を起こし、挿送を再開させる。ニスロクが声をあげるよりも早く、その白い背が快感に引き摺られぶるりと震えた。
「待、て、アガっ、ぁ、っく」
普段休ませてくれないだろう、と言ったもののそれはあくまで純然たる事実を告げただけで、仕返しをしてやろうという気持ちはアガレスには一切なかった。ただ、平素見ることのできない蕩けて疲弊したニスロクの表情に心の危うい部分を揺り動かされる。同時に、温かな粘膜に根元まで包まれていると充足感を感じる一方で、精嚢の辺りが疼き、じっとしていられなくなる。動物の如き欲求に突き動かされ、腰を振りたくて堪らなかった。思考を放棄することを魂が肯定していた。
「あ!…っく、う、ぅ゛」
パン、と肌が高い音を立ててぶつかった瞬間、ニスロクも絶えきれずまた裏返った声を漏らした。彼の爪が自分を叱咤するようにシーツを引っ掻く。それを無為にするかの如くアガレスは己を打ち込んだ。ピストンを繰り返すうち、跳ねる尻たぶの感触が堪らなくなる。癖になるな、この尻は──と本人が聞けば烈火の如く怒りそうなことを思った。
「っふ、くっ…き、さま、待てと、…ンン゛っ~~~…!」
「すまん。聞いてやれない」
ニスロクの背がぐっと丸まり、脱力する。また達したのだろう。そう気付きながら、アガレスは腰を振るのを止めなかった。深夜の静寂の中で肌がぶつかる音が部屋の四隅まで満たしていた。
結局アガレスは休憩を挟まずに五度射精した。追放メギドとはいえ体は普通のヴィータのはずなのに、どうしたことだろうと驚く。隣では純正メギドであるはずのニスロクが身動きせず寝そべっていた。彼が何度達したのかはアガレスにも分からないが本人にも分からないだろう。精根尽きたようで、口を開いてアガレスに文句を言うことはなかったが、代わりに閉じた瞼の上で深く眉間に皺を刻んでいた。
「すまなかった…少し無理をした」
アガレスはニスロクの顔にかかった髪を払って耳にかけてやり謝るが、眉間の皺は頑として解けない。
「ニスロク…」
血の気の失せた細面の頬に触れる。彼はやはり身じろぎをしない。褐色の指がなだらかな肌の曲線を滑る。反応のなさに、今度は唇でその頬に触れた。二度、三度、と少しずつ場所を変えながら口付けていく。まぶたに唇で触れると、ようやく金色の瞳がゆっくりとその姿を現した。
「…別に怒っているわけではない。抱かせてやると私が言った、その結果だ。貴様が欲情するのも仕方がない」
気怠さに支配された表情と口調で言ってからニスロクは、それより、と付け加えた。
「今のはなかなか良いな」
『今の』が何を指すのだろうとアガレスが動きを止めていると、ニスロクの手がその顎を捉え褐色の肌に口付ける。頬に二度、三度、そして慈しむように瞼へ。
「今度貴様が気をやっている時にしてやろう」
薄桃色の唇がその可憐さに似合わない悪い笑みを浮かべたので、アガレスもつられて笑った。
余談。ニスロクの精が甘かったのは本人曰く、「夜食にアイスハニーレモンを食べたからだろう」ということだった。
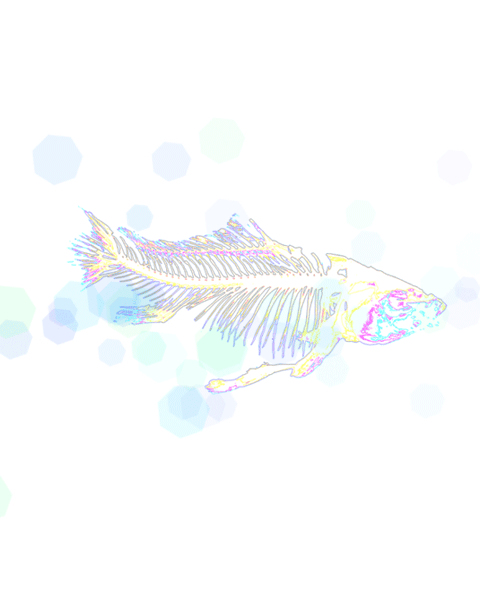
カテゴリー別人気記事